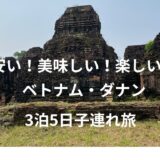少しづつ春を感じる陽気になってきました。
4月にお稽古はまだ炉のお手前です。
今日使うお茶は八女茶。
宇治茶は今、外国で大人気で先生も手に入れるのが大変なようです。
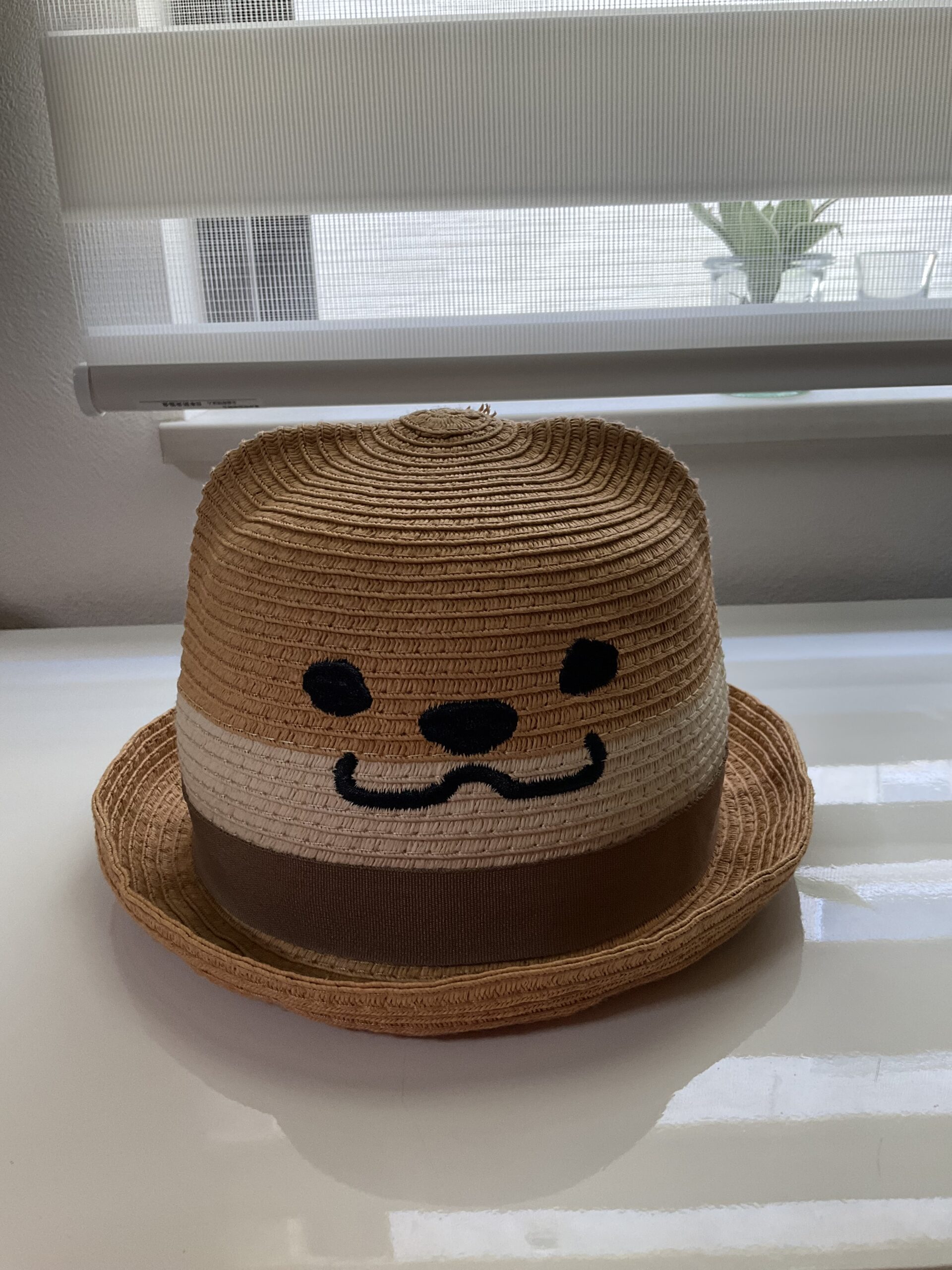
やめ茶ってなに?
八女茶は福岡が産地のお茶で宇治茶と比べるとまろやかなのが特徴です。
でも飲み比べないと分からないかな💦
お道具のおさらい
棚
更好棚(コウコウ棚)
裏千家の11世玄玄斎が好んだとされる。
調べてみると、つまり利休が好んだ3重の棚を好みで1枚外して2重にした棚ということ。
更に自分好みにしたってことですね。
特徴としてはやや小ぶりで、黒い漆塗りだけども棚いたの周りが赤いこと。
爪紅(つまくれ)というようです。
茶碗
渋草やきと京焼のもの。
春らしくたんぽぽや蕨が描かれていました。
棗
吹雪(上げに面とりしてあるもの)で春の蒔絵。
蓋に蝶が描かれて可愛らしかったです。
軸
「柳緑花紅」(りゅうりょくかこう)→「やなぎはみどり はなはくれない」と読み下す禅語。
11世紀の中国の詩人、蘇軾からの引用だそうです。
意味は「そのままの姿がすばらしい」、春に自然の
長谷川寛州の筆。
花はあずきやなぎと黒椿
畳床だったので花台は塗りのもの。
花入が釉薬を使わない焼き物のときは木台になる。
濃茶の入れ物は備前の火襷(ひだすき)。
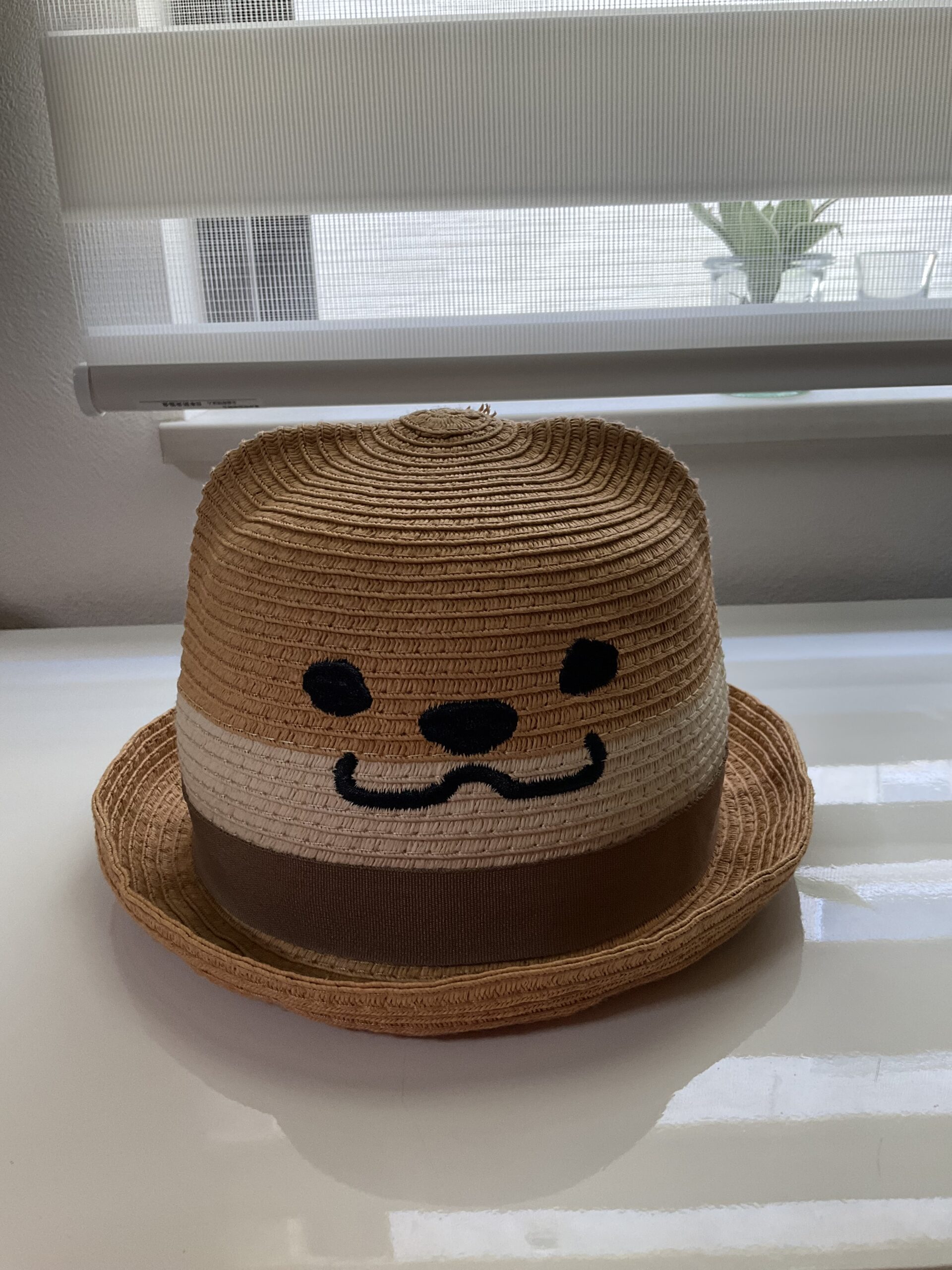
漢字ムズ!
備前の焼き物は素地に藁を巻いて焼いた際にできる模様のこと。
タスキのように見えるのでこう呼ぶそうです。
文琳型。
「りんご型なのよ」と先生がおっしゃっていた。
そして今日の茶杓の名は「雲錦」。
毎度「御茶杓の御名は?」との問答がなんとなくしか分からなかったけど
茶道でこれを聞くのは「今日の一席」のタイトルを聞くんだと教えてもらって納得。
一期一会の、一席をとても大事にしている姿勢がよくわかりますよね。
話がそれてしまいました。
「雲錦」は「吉野山の桜は雲かと見え、竜田川の紅葉は錦の如し」からきていて、桜と紅葉と一緒に描かれている模様を雲錦模様と言います。
覚えることがいっぱい。
4月 ②
2回目も早くも終わってしまいました。
今回で炉のお点前は終了です。
扇子の置き方
茶道では扇子は入室の際や、お道具を拝見するとき自分の前に置いて使うことを以前書きました。
置き方は親骨を上にして置く。
「こうやって踊りの時も広げるでしょ」
茶碗
コヒキ写し・・コヒキは朝鮮のもの
水差し・・とび青磁
棗・・花鳥図(牡丹とうぐいす)
花鳥図・・富貴 床の間によくある
棚が四本柱のときは水差しの蓋は三手で開け閉めする。
今日は濃茶をオモアイという二人で飲む作法を見せていただきました。
コロナになってからずっとやらないでいたけど最近ではどの流派も初めているそうです。
見ているとどうやら初めから一椀に飲む人数分のお茶を点て、飲む方は回し飲みで一緒に楽しむようでした。
今日のお花は白百合芥子を備前の蔓首に生けてありました。
とても楚々として素敵でした。
来月からは風炉になるのでその前に予習しておくようにと言われました。
結局一連の作法を覚えられずに次へと移ってしまいますが 諸先輩がたは一年はしょうがないのよ、みんなできないまま終わるんだから、と励まされ終了しました。