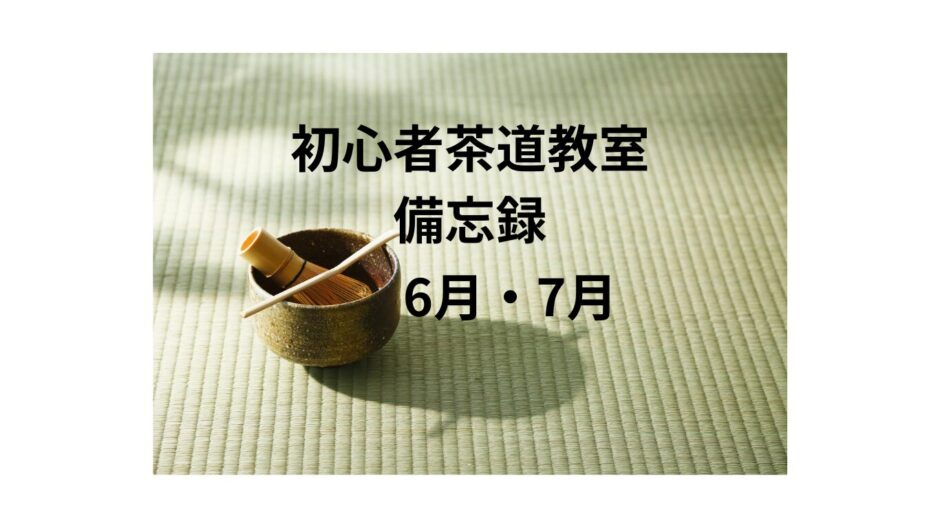6月、一回お稽古をお休みしてしまい💦7月のお稽古時はすっかり手順を忘れてしまっていました。
記事にするのも相当遅れたのでほんと記憶がわずかですがこれ以上忘れないように6月、7月のお稽古で習った作法やお道具を記していこうと思います。
まずはお道具から
棚もの
三木町棚・・大工さんがいろんな木を組み合わせて作った四角い棚
江岑棚(コウシンダナ)・・上に引き出しがある棚(棚の中に棗を入れたりする時もある)
四角い棚は陰だから柄杓を飾る時柄杓は上むき(陽)にする。
水差し
盆・・黒い塗りのお盆を伏せて載せた時、帛紗を金魚の形にして飾っていました。
3手で取り、蓋を水指の奥へ立てかけます。
ぴったりサイズの螺鈿の柄の時・・・絵が描かれた蓋の時にはその上には何も飾らない。
棗
6月のお稽古では金輪
輪島のホウショウ
蛍と葦の模様でした。
ちなみに6月は源氏蛍(少し大きめ)、7月8月は平家蛍(少し小さい)だそうです。
お薄器
水滴・・・四滴のうちの一つ
四滴とは
- 茶道の陶磁器製の4種類の薄器を指す総称
- 蔓付(つるつき)・手瓶(てがめ)・水滴(すいてき)・油滴(ゆてき)がある
水滴の扱い方
注ぎ口の向きがポイント⭐️
茶筅と並べておく時など何かと置く場合、必ず注ぎ口と向かい合うようにおく
お茶を立てるために取る時、手のひらに乗せ口を自分の方に向ける
拝見でお道具を見る時次の人(進行方向)に口を向ける
茶杓を置く位置は水滴の蓋のつまみの左側
⭐️水滴はお薄器でも濃茶の時でも使える
水差し
白い焼き物だったけれど「のあと」が付いてる、と教えていただいた。
のあとというのは焼き物を重ねて焼いた跡のことだそう。
日本では焼き物は一つずつ重ねないで焼くのですが大陸で雑器として焼かれるものは重ねて焼かれることがあるとのこと。
お軸やお花、茶碗はもう時間が経って柄しか覚えてないのですが、とにかく6月、7月のお稽古で思ったことはとにかく柄杓の扱いを覚えることと、呼吸を意識すること。
先生曰く、
「主婦の仕事してるんじゃないのよ。手順はただやれば良いんじゃないの。魅せることが大切なのよ。能の呼吸のようにやってちょうだい」
なるほど、能ね・・。
道は長いなぁ。