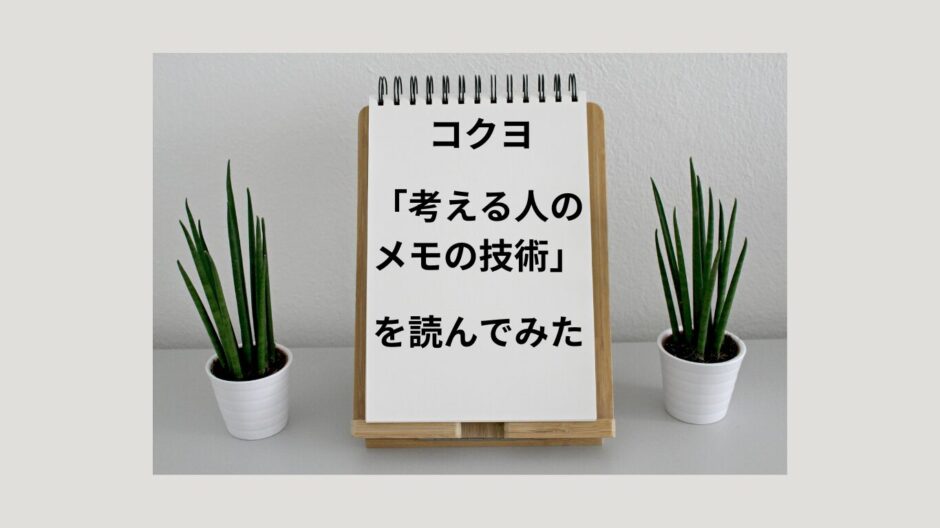「考える人のメモの技術」はあの有名な文房具会社、コクヨで働く下地寛也さんの書いた本です。
私は長年手帳を使っていて、ちょっと気になって手に取りました。
なぜメモが必要なの?
そもそもどうして書くことが必要なのか。
そんなふうに思う人もいるかもしれませんね。
書くということは頭の中のモヤモヤをはっきりさせ、現状の把握をするためにとても役立ちます。
私には中学生の息子がいるのですが、
いつもテスト前になると息子は毎回「どうしよう。何をやったらいいかわからない。終わった・・。ねえ、何したらいいと思う?」と訴えてきます。
「何をやったらいいなんて、何がわからないの?」
と聞いても
「全部!」
「何をしたらいいんだ!」
とこの問答をテストの最終日まで何度もします。
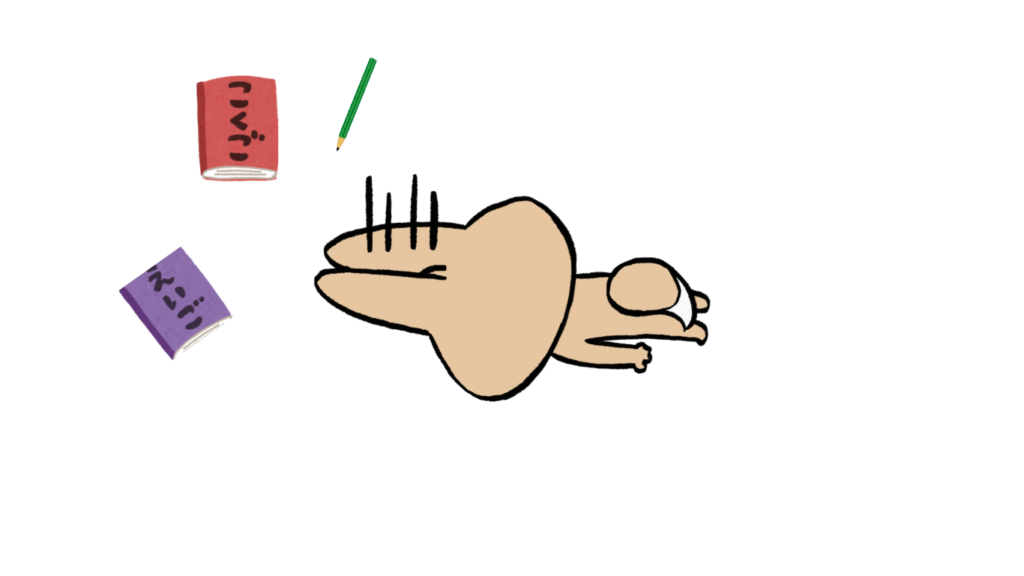
「いつまで同じことをやってるの?いいからわかっていることを全部書き出しな!」
同じことの堂々巡りについイライラしてしまいます。
頭の中で考えてても思考はぐるぐる回るだけで進まず、時間だけが過ぎていきます。
パニックになった時はとにかく紙に書き出しましょう。
書き出すことはわかっていること全部です。
自分がわからないこともです。
試験であれば
・試験の日付け
・あと何日あるのか
・学校から帰ってきてできる時間はどれくらいか。1時間なのか2時間なのか、はたまた30分しか取れないのか。
・範囲はどこなのか
・どの部分をやってあるのか
・各教科の中で苦手なところはどこなのか(→これも全部、とよく言われますがランキングをつけろと言います。)
・今の気持ち(何が心配なのか)
などなど。
書き出すことのメリット
書き出すことのメリットは
・今の現状を文字通り目にして把握できること
・客観的に見れる
・頭の中での堂々巡りをやめれること
→思考の負担が減ってそれだけで楽になり、前に進むことができます。
この状態になればもう、作戦を考えるだけなのです。
尚、気持ちを書き出すことは「心の中にランタンを灯すこと」と『書ける人だけが手にするもの』齋藤孝 でも書かれていました。
前に記事にしたので興味がある方はこちらも読んでみてくださいね。
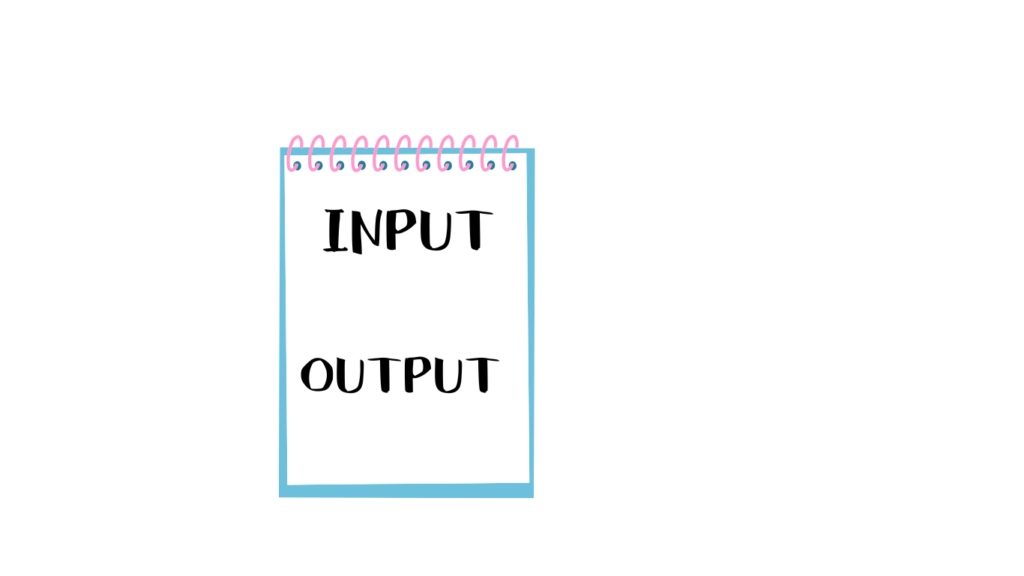
2種類のメモ
メモには2種類あって一つはインプットのメモ、もう一つはアウトプットのメモだそうです。
インプットのメモは
言うまでもなく「覚えておきたい、忘れてはいけない情報」「ちょっと気になったこと」など。
アウトプットは先ほど書いたように自分の気持ちや情報の整理、またはひらめきの創造だったりしますよね。
この2つを意識しながらメモを取るとよさそうです。
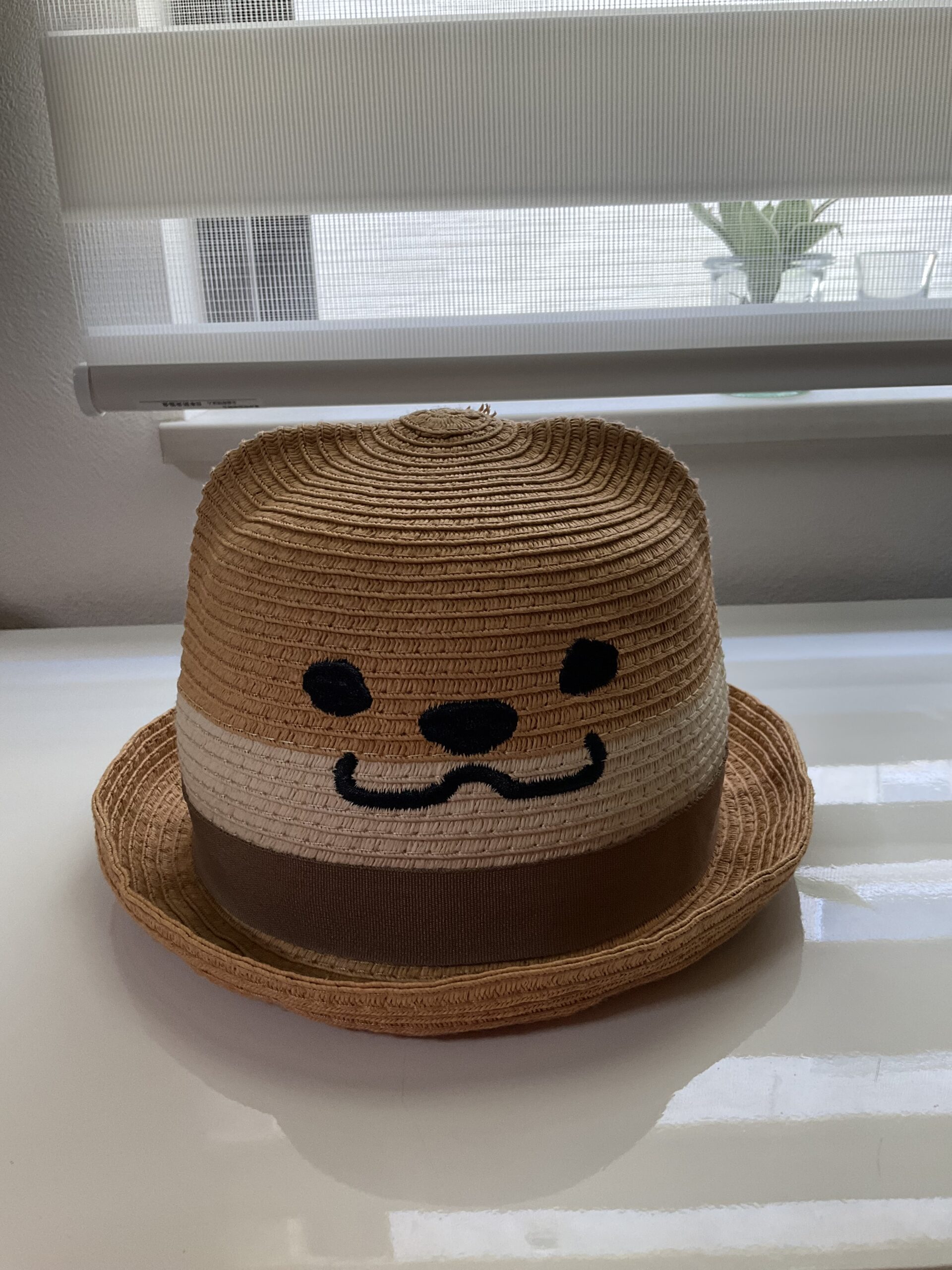
これはなんとなく分かる。
メモの取り方はさすがコクヨの社員の方達でそれぞれオリジナルの取り方があるようで、その社員の方たちのから色んな種類のメモ帳、ノートが商品としてすでに開発され、市場で売られていました。
(↓参考までに)
色々あるので自分に合うメモ帳を探してみてくださいね😊
メモは手書きが良い
メモはスマホでもできるけど手書きのいいところは
①自由度
②一覧性
③記憶定着
④創造性
の4つ。
私はこの中でも特に①自由度、②一覧性、④創造性に手書きのメリットを感じます。
①自由度
手書きの方が圧倒的に優れている点は『スピード感』。

共通点を見つけて線を引いたり、グルグル丸で囲ったり、思いついたことをどんどん思ったままに表現していくのは手書きのほうが圧倒的にスピードが違います。
ちょっとイラストを書き足してその時のイメージを残しておいたりもすぐできます。
②一覧性
これは何かを考えたりする上でとっっても大事なポイントだと思います。
パソコンやスマホの場合、画面の解像度の関係であまり細かい文字は見えません。
どうしても一覧で見られる情報量が限られます。
スクロールしながら見るのってちょっと面倒なんですよね。
子供の学校のお便りもペーパーレス化で学校のアプリで送られてくるのですが、とっても見づらくて紙で欲しいな〜と思ってしまいます。
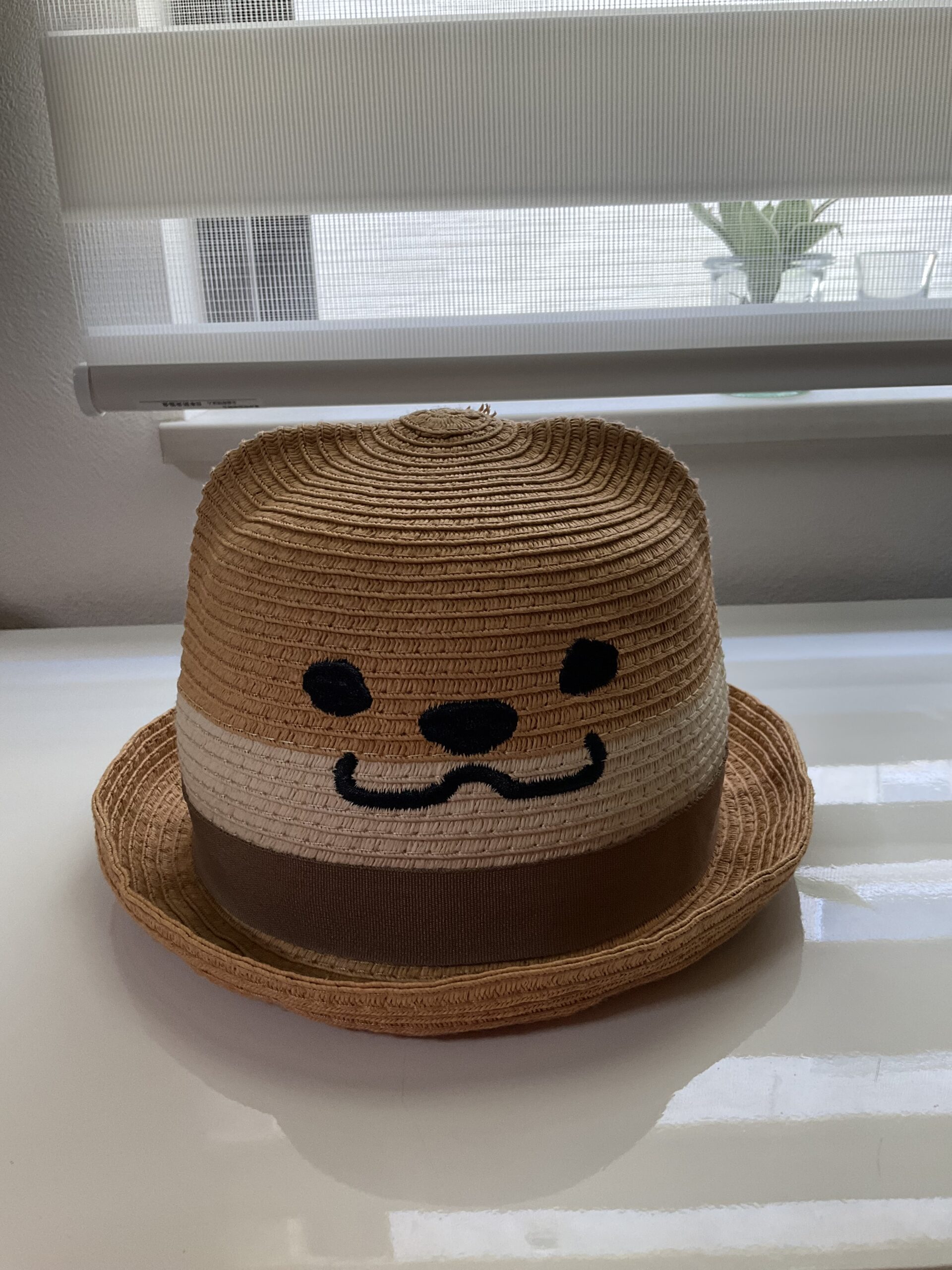
老眼だともっと困る💦
④創造性

メモを手書きで書いているとそのうちそれぞれのつながりが見えてきたりどんどん思考が発展していきます。
これもいいところ。
(ちなみにこれは本書には書かれていませんが、紙の方がデジタルのものより考えたり認識するのに良いそうです。
以前、このことを耳にして面白いなと思って調べたところリコーさんのページに情報がありました。)
メモの取り方
メモするときは必ず「気づき」もメモしておくこと。
これは一番大事なことかと思います。
ちょっといいなと思った情報、今度やってみようと思ったことをメモしても後で見返すと何のことだかわからないことってありませんか?
書き記しておこうとしたくらいです。
きっと何かしらのインスピレーションを受けたのだろうと思われます。
しかし、
人間は忘れる生き物です。
自分が書いたことでも「気づき」(自分の気持ち、その情報から閃いたことなど)が書かれてないとそのメモが何を意味するのか、思い出すのは難しい。
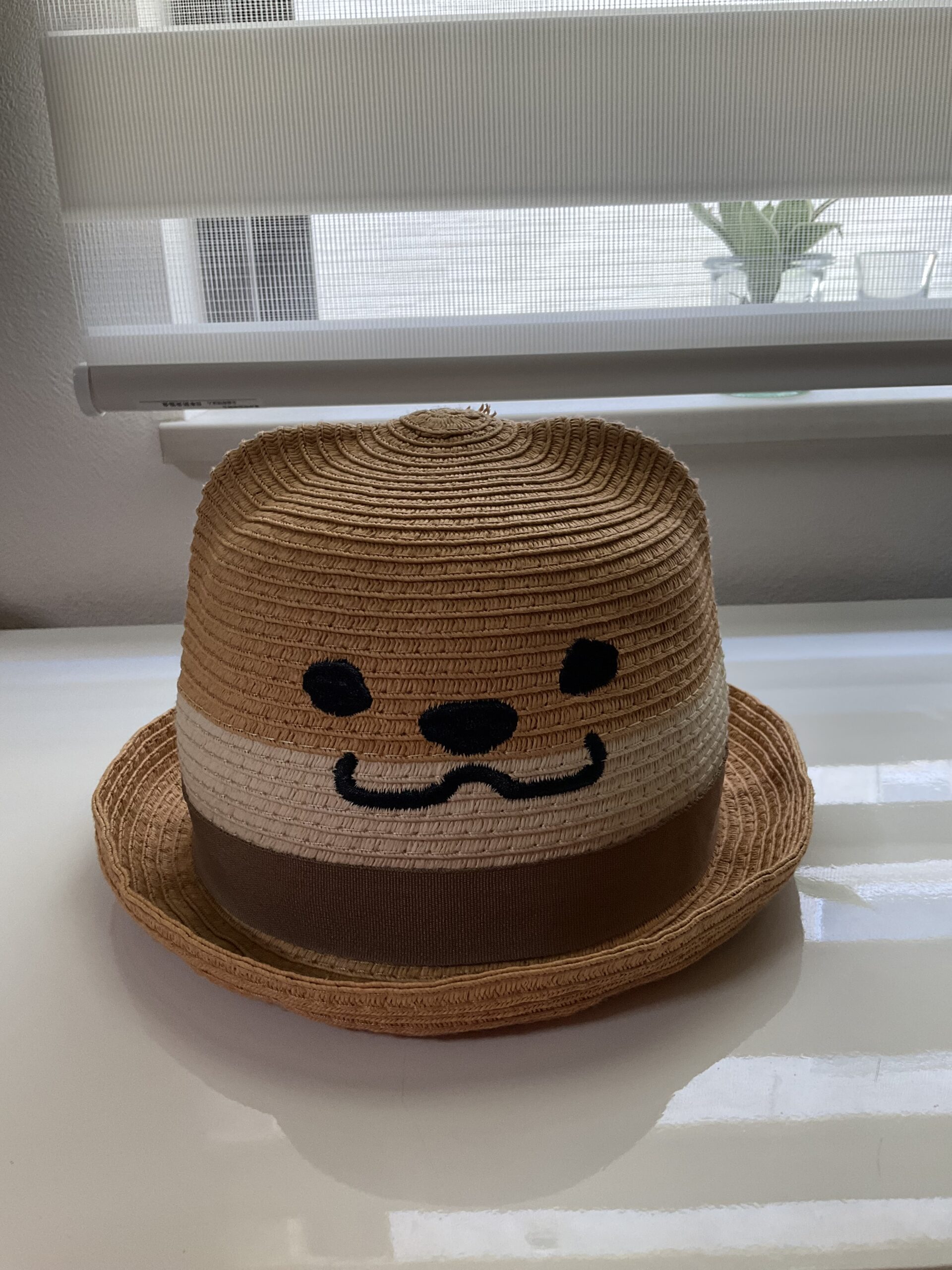
年のせいだけではないはず。
そしてこれはとっても勿体無い。
だって有用な情報だったからメモしたんですもんね。
〈スマホで情報の写真を撮った場合〉
たくさんの情報がある時(記事や視覚的情報)はスマホで写真を撮っておくと便利ですよね。
その時はメモ(私の場合は手帳)に、スマホ/写メ/日付 など書いておくとスマホの中で埋もれたままにならずに済みます。
よくありがちなことですが そうしないと撮ったことさえも忘れてしまうんですよね・・😭
〈アウトプットするときのちょっとしたポイント〉
なんでもいいから(仮)でこれから書こうとすることのタイトルをまず大きく書くこと。
ここを目指してますよ、と自分にわかるようにすることがちょっとしたポイントでした。
じゃないとどんどん話がずれていったりしてしまうからだそうです。
最後に
以上が「考える人のメモの技術」から得た学びポイントです。
何だか色んなことに使えそうですよね。
ちなみに学びポイントには書かなかったのですが、読書にももちろん使えます。
本に直接書いても良いですが、最近私がやっているのは附箋を貼ってそこにメモすることです。
これだと付箋が貼ってあるのでページを探さなくていいというメリットもあります。
集まったメモを見ると自分の新しい発見にも繋がりそうですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました😊