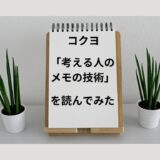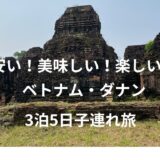今日は昨日までの暖かさとは打って変わって雪予報の1日でした⛄️。
部屋には桐箱が置かれていました。
旅箪笥というそうです。
ラーメン屋の出前の箱みたい。
旅箪笥とは豊臣秀吉が小田原の陣の際、利休が考案して持っていったもの。
屋外でお茶を点てることを野点と言いますがこの旅タンスを使うのは芝点と言うそうです。
開け方、閉め方も教わりました。
来年まで覚えているかな・・。
そして3月3日の今日は菱形の水差し!
ひな祭りだから菱餅の形の水差しなんですね✨
なんか嬉しい😆
釉薬がとても素敵な瀬戸のものでした。
茶碗
黒い塗りで貝の柄。
蛤かなと思ったのですが
横に海藻の模様があり、そういうものはミル貝だそうです。
棗
ベージュに桜草。蓋を開けると中が黒の塗りで洒落ています。
お軸
お内裏様とお雛様の絵。
奥村ドウキョウ?有名な画家のもので京雛なので反対の位置に書かれています。
花入
とても素敵なものでした。
中国の足が三本のものです。
一本足を前にして生けるようです。
濃茶の茶碗は井戸で萩
井戸茶碗とは16世紀に朝鮮半島からきたもの。
高台が高くなっているのが特徴で素朴な味わいで武将や茶人に人気だった。
茶入れは信楽
三島の写し
花三島
オシフクは織部どんす
流水に梅
色んな流派があるけれど織部は武家流なのでオシフクも左でなく右側につける
左は刀を刺す方だから。
今日先生から言われたことは
「もっと一つ一つを丁寧に」
「仕事じゃないのよ」
「間を作るのよ」
「あなたのお茶の立て方は何にも魅力がない」
ちゃきちゃきした先生なのではっきり言ってくれます。
ようやく手順の指摘からこういう言葉をもらえるようになりました。
3月 ②回目
なかなか投稿できず・・・2回目も終了してしまいました😅。
この日、一番目を引いたのは釣り釜でした。
天井から鎖でお釜が吊るされています。
これは3月が暖かい日もあれば肌寒い日もあることからお釜の下の火がゆらゆら見えたり隠れたりしてこの時期にぴったりだということで3月のお茶席で見られるものだそうです。
風情がありますね✨
4月にはもう火は見せないようにするので3月、きちんとお休みせずに出れて良かった✨
そして旅箪笥が今日もありました。
先輩のお手前では毛せんが引かれてある想定で中板を出して棗や茶碗の下に敷いていました。
お釜
天井から吊るされているお釜はナツメ型のアラレ釜(周りがフツフツと点がついてる)
水差し
アンナンの写し
安南とは今のベトナムあたりにあった昔の国の呼び名。
そのころのものを模して作られたものということです。
春霞のようなボヤッとした感じの柄でした。
「染め付けはまだ寒々しいからね」と先生はおっしゃっていました。
茶碗
白磁。人間国宝の方のものだそうで白くて形が可愛かったです。
お茶では特にお茶会では貴重なお道具でのおもてなしもあるので指輪は時計などは外しておかないといけません。
傷をつけてしまっては大変です。
もう一つの茶碗は群馬県のしぶき焼きだそうです。
表面はガラスでコーティングされているような感じで絵もその上から描かれているように感じました。
棗
黒棗のあけぼの柄。
枕草子の「春はあけぼの」から、今日はこちらを選んでくれたのでした。
お軸
「楽在一椀中」
「楽しみは一椀の中にあり」という禅語。
椀はお茶の椀だけでなくご飯の椀でもあり、その一椀を心から喜び楽しもうと味わおうという気持ち
ほんとのメモ書きになってしまいましたがひとまず投稿します😓