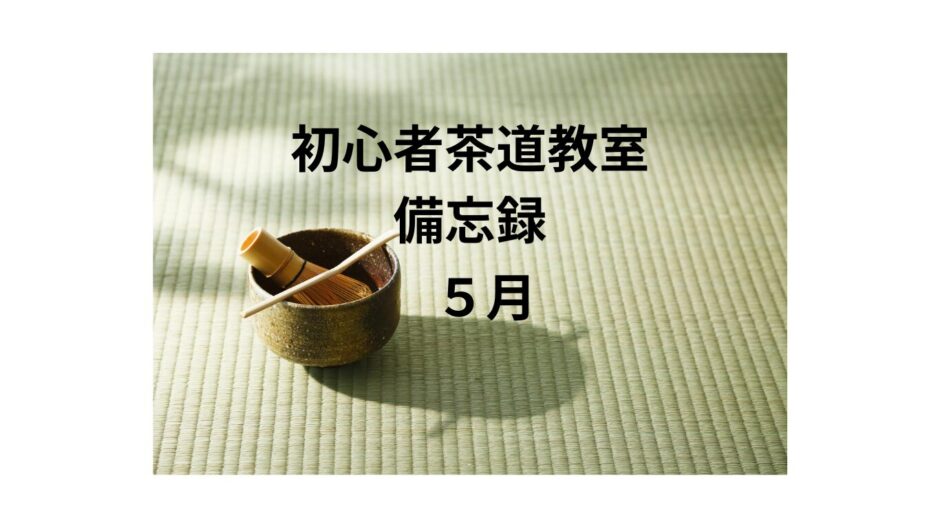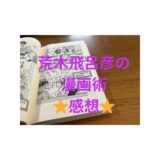5月になり、今日から風炉のお点前に変わります。
道具の置く位置が変わり、それにより少しやり方も変わります。
道具自体も変わるものもあるので今日は順番に復習してみようと思います。
①お釜
風炉のお釜は今までよりもずっと小さなものになりました。
炉のときはお釜は掘りごたつみたく畳の一部に凹んだところがあってそこにセットしていたけれど今は畳の上に敷物を敷いてその上にお釜をセットしています。
から鉄釜?の時は板敷らしいデスが今日は織部焼きのものを敷いていました。
瓦を敷くときもあるとのことです。
そしてどぐう?を5月は普通使うそうで、これは灰が見えるのがご馳走なのだと先生は言っていました。
②柄杓と柄杓置き
柄杓置きも釜の位置とともに変わって釜の左側になりました。
釜の下の板から三分出すように置きます。
柄杓は釜の上へ中央まっすぐに置きます。
③花入
5月から籠を使っていいそうで、今日は籠の入れ物でした。
道具の変化はそれくらいかな。
もう少し気温が上がってくるとお茶碗が変わってきます。
場所の変化
以前も記事に書きましたが、客から火が遠くなるようにお釜は奥の場所になります。
お釜の右側に水差しがきます。
作法の変化
水差しはお釜の鐶付と水差しの蓋が真横にくるように置きます。
自分の右側にくるので蓋を取るのは二手で取る。
そしてこの辺が細かくてザ・茶道という感じなのですが蓋を返すときに
夏は右膝の角で返し、冬は左膝の角で返す。
私のような初心者はどっちでもいいんじゃ?と思いますが、ただお茶を飲むだけでなく一連の動作を見せる(心地よく美しいと感じてもらう)ことが相手への心尽くしであるのでいい加減にやりたいようにやってはダメと厳しくおっしゃってました。
柄杓の使い方
お釜が出ているので、お釜に乗せた柄杓は中に浮いていて今までとは使い方が少し違います。
風炉の時は3つのやり方を覚えます。
①かざし柄杓・・お湯を入れた時(茶筅通しなど)
②結び柄杓・・・茶を点てるお湯を入れた時
③ひき柄杓・・・水を入れた時(「お終いください」のあと)
この3つの柄杓の扱いは弓道の動作から利休がとったものだそうです。
今日の道具
茶碗
・九谷焼 あやめの模様
・オガタケンザンの写し
江戸時代の名工。尾形光琳の弟。
社交的な兄とは違い早くから隠居生活をしたが、兄弟仲はよく合作もいくつかある。
野々村仁清の近くに住んでいたこともあり陶芸は野々村仁清から教わったのではと言われている。
棗
長棗であやめの蒔絵に輪島の漆塗り、ホウショウという塗り師のもの
お軸
「行雲流水」雲水さん(修行僧)の絵が描かれた短冊
空を行く雲や川を流れる水が絶えず同じでないように物事をこだわらず、自然に任せることや、自然の雄大さを表す言葉
お花
花筏?
しらゆきげし

リョウブ

籠の花入だから板は無し
②
道具
茶碗
青磁の茶碗・・少し重みがある。日本のものと違うのは高台をみるとわかるそう。
高台をくっ付けてない。
外に千鳥の模様、中にまつが描かれている。→浜千鳥
お薄器
棗と違って乾漆作りの籠なつめ
乾漆作り・・木型を作りその周りに和紙をこよりにしたものを巻き付け、漆を塗る。
→あとで木枠を抜く
奈良・平安時代に多く用いられたアジアの手法らしく、仏像もこのやり方で多く作られているとのこと。(確かにこれだと重くない)
蓋はオシドリの蒔絵
オシドリは漢字の中にエンオウという漢字
竹内幸斎(石川県の山中市)の写し?
濃茶入れ
黒織部の澪標柄
「澪つ串」(つは助詞)でミオというのは水脈。つまり水路を船が通る時の目印としてあった杭のことらしい。
【身を尽くし】と和歌では掛けられて読まれる。源氏物語の第14帖から来ている。
チュウコウメイブツー小堀遠州のあと
オシフク 金剛金山・・金剛太夫(能を舞う人)の好きだった柄
お花・・紫蘭
お点前の座る位置
何か飾ってあって持ってるものが一つの時は左の釜と右の棚の真ん中正面に座る。
水差しを取る手は3手。
茶碗と棗の二つを両手に持っているときは棚の正面に座り、そのまま置く。水差しは近いので蓋を取る手は二手。
濃茶のみんなでいただくやり方も教わったがまた今度。
とりあえず柄杓の3種類の扱いを次回までに覚えよう!