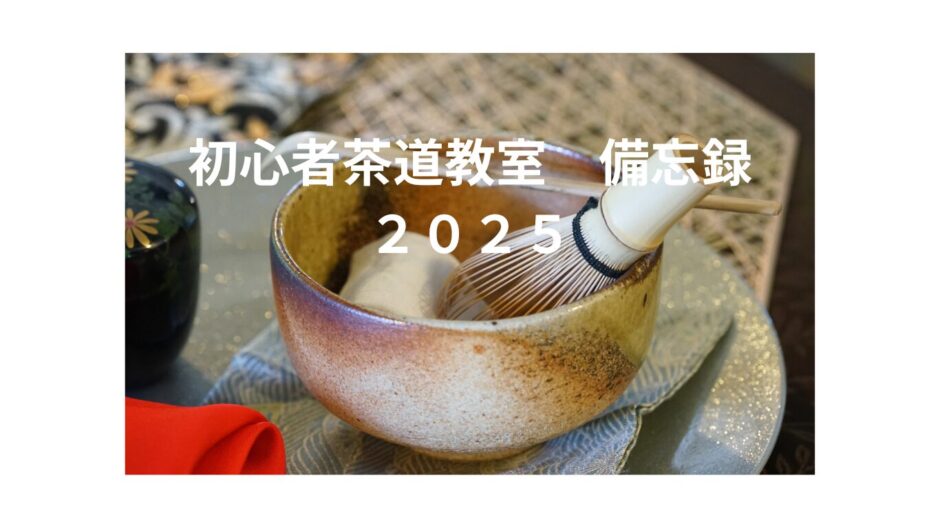2025年、茶道教室が始まりました!
普通、茶道では年初めに初釜というものがあります。
でもちょっとそちらには参加しなかったので普通のお教室の始まりです。😊
1月もすでに2回のお稽古を終えました。
すぐに投稿できると良いのですが、相変わらず遅くなってしまいました。💦
なので2回分まとめて書きます。
お道具、作法に分けてメモしていきますね。
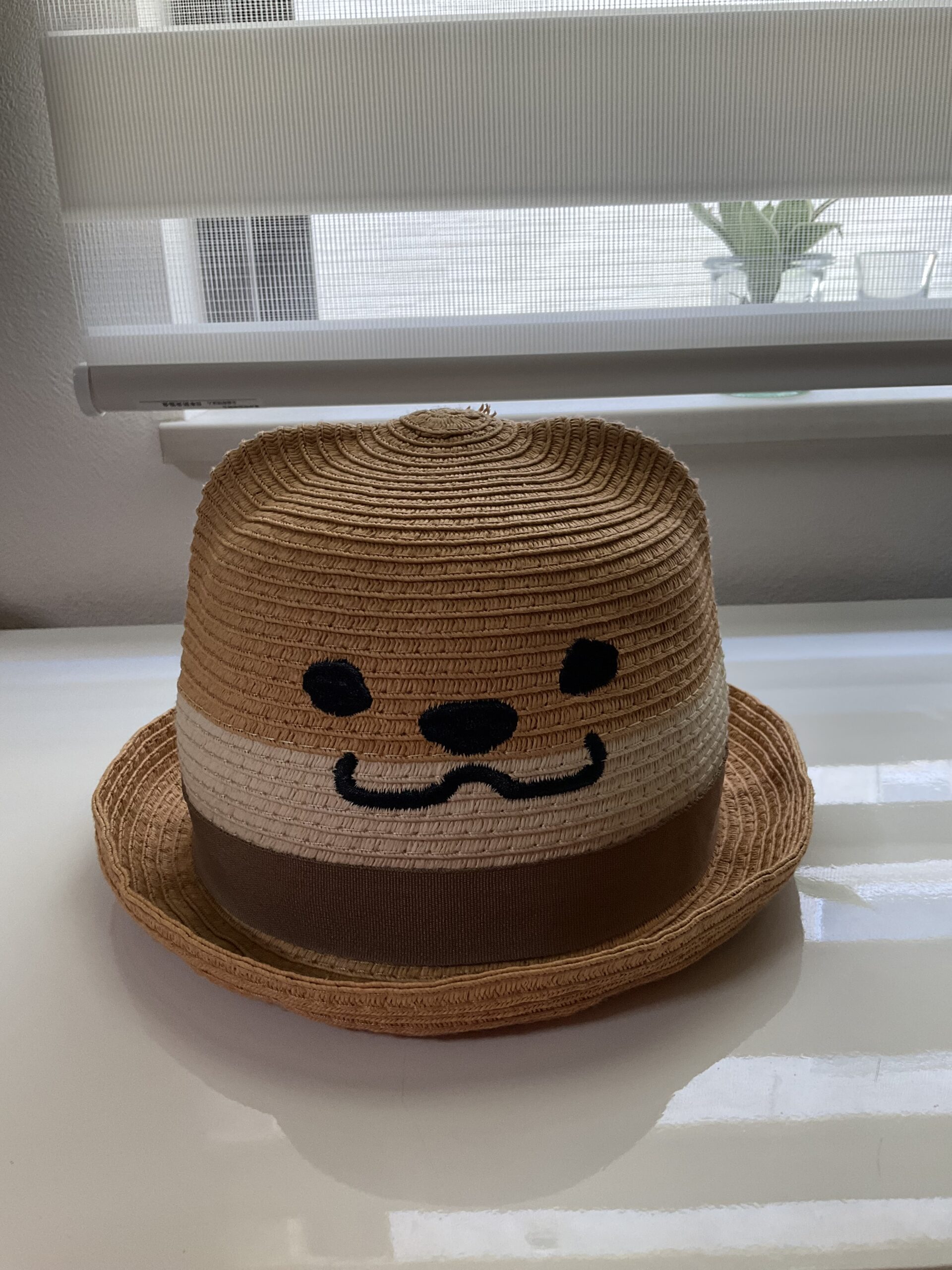
まずは今回使ったお道具から行くよ!
〈お道具〉
棚もの
年初めということもあってまず目を引いたのがとても素敵な棚ものでした✨
三友棚だそうです。
裏千家、表千家、武者小路千家の三千家の融和を表し作ったもの。
板の部分は松で出来ていてそこに二本の竹の柱、上の台の部分は梅の木で出来ている。
おめでたい松竹梅ですね。🪭
水差し
これまたみたことない立派な物。
焦茶のように見えたけれどよくみると紫の焼きものに水色で雲の模様やラーメン屋によくある模様が描かれていました。
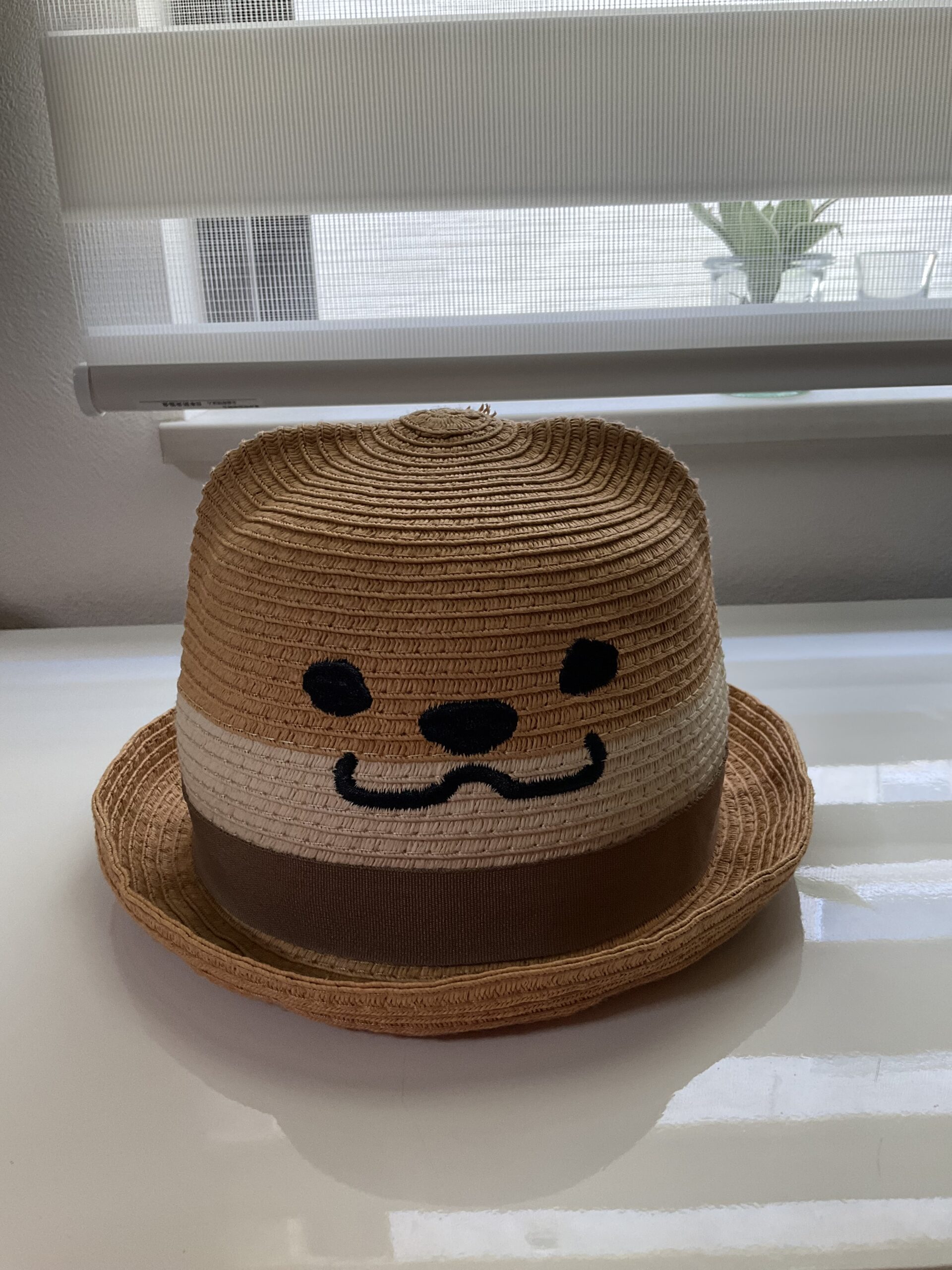
ちなみにあの模様は雷紋だよ⚡️
偕楽園焼きとおっしゃっていました。 コウチより華やかだともおっしゃってたけどコウチは今度調べます😅
紀州の3大焼き物 紀州徳川家のお庭焼き
初めて聞いた名前でてっきり茨城のものかと思いましたが、紀州の3大焼き物 紀州徳川家のお庭焼きだそうです。
2回目のお稽古では九谷焼の水差しでした。
おもとの絵が描かれているもの。先生曰く茶色とグリーンの組み合わせはよくあるそうです。
お釜

初めてみた蓋が四角いおかま。四方口と言うのかな?(上のお釜のことではありません)
先生曰く「松風もお釜によって違う音なの。だから色々なお釜を使うのよ。」
なるほど。
松風というのはお釜からでるシューっとした音。
音に名前があるのって素敵ですよね✨
しかも「松風」なんてかっこいい!
棗
棚に飾り置きされていた棗は少し大きく、下の方から上の方へと黒と赤のグラデーションの物でした。
蓋が平らな平棗で「あけぼの」と言う名前がついていました。
確かにこれから夜が明けようとする感じがしました。
開けると綺麗な銀色の塗りにハッとします。
とってもお洒落〜!😆
この中の銀の塗りになっているのは石川の輪島塗りだそうです。京の漆塗りとは違うそう。
京の塗りと違うのはしっかり塗ってあるとのことです。
2回目のお稽古でも平棗を使いました。
こちらは小ぶりな昔のもの。
黒の漆の下の朱が透けて出ているような感じでした。
幕末の頃のものだそうでこういう年代物は「古いものですね」などとは言わず、「時代が下がったものですね」という方が良いそう。
柄杓おき
いつもと違って白い塗りの焼き物で松の絵が描かれたものでした。
先生は「松にも色々あるのよ。描かれている松を見て唐松、ネヒキマツ、など何の松かわかるようになりなさい」
とおっしゃっていたので少し松の絵柄について調べてみました!
そもそも松は千年の樹齢を保つことから長寿の象徴として使われています。
若松・・・芽生えてまだまもない若い松
老松・・・年月を経た風格のある松
唐松・・・松葉を上から見て菊花のように丸くしたもの
雪松・・・松の葉に白い雪が積もった様子を描いたもの
根引(曳)松・・・根がついたままの松。根がついていることから「地に足がついた生活を送れるように」や「成長し続けるように」ということで京都の正月飾りで使われたりするらしい
掛け軸

「松樹千年翠」・・・松の緑はずっと変わらないこと
こうして書いてみると今月のテーマは松だったんですね。
花入
おうひ一平?蝋梅
2回目は梅もどき風のものと寒菊 が桐の花入に飾られていました。
茶碗
絵唐津のもの
唐津焼とは佐賀を中心に作られている焼き物で国の伝統工芸品に指定されているもの。
荒い土を使った素朴な焼き物で、ここに絵を描かれているものを絵唐津と言うそうです。
絵もいろんな色は使わず茶色のみで描かれている。
今回使った茶碗は縁の飲み口に濃い茶のラインが引かれていました。
縁だけ黒っぽく見えるのは「皮鯨」と教えていただきました。
クジラはお腹が白いけど海面からは背の黒い部分しかみえないことからこう呼ぶそう。
もう一つの茶碗は金襴手
染め付けに赤絵で寿の文字
磁器。陶器と違って高い音がする。
もう一つ黒い茶碗も2回目で使いました。
かわいいねじれ梅の形のもの。
高台の脇に◯楽とあり。
献上品の場合は高台の中に二重丸で落款があるそうです。
濃茶のお茶入れ
丹波焼 形はずんきり
2回目は赤楽のもの。
陶芸は必ず一度は楽焼をするそうで、4代五条坂のキスケ 江戸時代のものでした。
オシフク
波状紋 梅花金蘭 青海波と似ているけど違うみたい
作法
お薄の一連の流れは間違えながらもなんとかできました。
ただところどころ雑になってしまうので
先生からは「間違ってもいいけどゆっくりと丁寧に、綺麗に見えるようにやるのよ。」とのアドバイスをいただいきました。
忘れてしまうのは
・お茶を立てた後茶杓を外すと同時に左手も外すこと。
・水差しからお釜に水を足すときは柄杓は棗と茶碗の間を通るように持っていく。
・大きい平棗を扱う際、左手の親指を蓋の奥がわに触れてから包み込むように持つこと。
この親指をチョンと触ってから持ち替えるのは何故だろう?
〈お道具の拝見の際の注意〉
・おしフクをみるときは底の部分を摘んで持つ。
「汚いものをつまむ感じよ」とのわかりやすいアドバイスを受けました。
若干違うけど😅。
・オシフクの袋の中の布は袋の口を広げて見たりしない。間からそっと覗き見る感じ。
→年代物だと生地が破れてしまったり壊れてしまうため。
確かに大切に長い年月使われているものもありますもんね。
納得。
1月はこんな感じでした。
最後までお付き合いくださりありがとうございました😊